スマホで健康保険証を提示できる「スマホ保険証」が全国で順次運用を開始したものの、実際の使い勝手には賛否が分かれている。
この仕組みの特徴と課題を整理し、現場の声や最新の状況をもとに、スマホ保険証の利便性と使いにくさを解説する。
スマホ保険証とは
スマホ保険証は、マイナンバーカードの健康保険証機能をスマートフォンに登録し、顔認証付きカードリーダーにかざすだけで健康保険証として利用できる仕組みである。
2025年9月19日から、対応機器を導入した医療機関や薬局で順次利用が可能となった。
導入の背景
マイナンバーカードの普及促進と、医療機関での受付業務の効率化を目的に、スマホ保険証の運用が決定された。
スマホ1台で保険証を携帯できることから、カードを忘れる心配がなくなる点が大きなメリットとして期待されている。
スマホ保険証のメリット
スマホ保険証には以下のような利点がある。
持ち運びの手軽さ
スマートフォンだけ持参すれば保険証として使えるため、財布がかさばらない。
マイナンバーカードを別に持ち歩く必要がない。
受付手続きの簡略化
従来のカード提示に比べ、顔認証付きカードリーダーの操作により受付が完了する。
事前に登録が済んでいれば、窓口での手続きがスムーズになる。
医療費控除・限度額認定の連携
オンライン資格確認システムと連携して医療費控除や限度額認定証の申請が簡単になる。
確定申告時の手続きの負担が軽減される可能性がある。
スマホ保険証のデメリットと課題
一方で実際に使ってみると、下記のような使いにくさや不安が報告されている。
利用可能な施設が限定される
顔認証付きカードリーダーやスマホ用リーダーを導入した医療機関・薬局はまだ一部に限られる。
事前に対応状況を確認しないと、従来の保険証を求められるケースがある。
高齢者・機械操作が苦手な人にはハードルが高い
スマホの操作に慣れていない高齢者などは、アプリの起動や顔認証操作を難しいと感じる場合が多い。
実際に「スマホ自体、使いこなせていないので難しい」という声も聞かれる。
事前登録の手間
マイナポータルアプリでの健康保険証利用登録や、生体認証用パスワードの設定など、初期設定に数分から十数分を要する。
紛らわしい設定項目に戸惑うユーザーも少なくない。
システム障害・機器トラブル時のリスク
オンライン資格確認システムやカードリーダーの故障、ネットワーク障害が発生するとスマホ保険証が使えず、従来の健康保険証が必要になる。
システム障害時に健康保険証を持参していないと、10割自己負担となる可能性も指摘されている。
セキュリティ・個人情報管理の不安
多くの個人情報をスマートフォンに登録することへの不安を抱えるユーザーもいる。
紛失・盗難時の悪用リスクや、電子証明書の有効期限切れも懸念材料だ。
まとめ
スマホ保険証は持ち運びの手軽さや医療手続きの効率化といった魅力的な機能を備えている一方で、導入医療機関の限定、初期設定や操作の難しさ、システム障害リスクなどが使いにくさとして浮き彫りになっている。
これらの課題が解消されるまでは、従来の健康保険証と併用し、事前準備を徹底することが利用者の負担を軽減する最善策と言えるだろう。
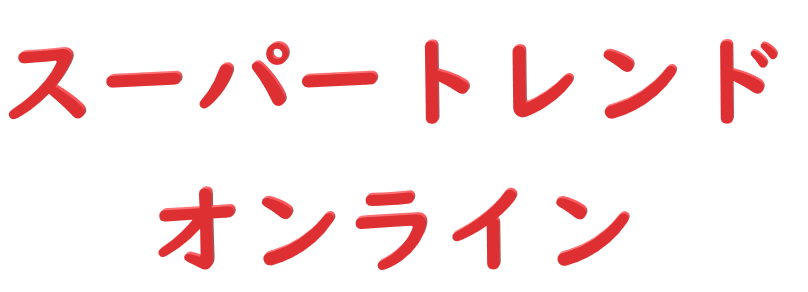
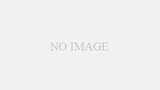
コメント