ファイナルファンタジー愛が生んだ奇跡のコラボレーション
堂本光一の音楽活動において、最も話題となったのは2021年の5thソロアルバム「PLAYFUL」におけるスクウェア・エニックスとの歴史的コラボレーションだった。
このコラボが実現した背景には、堂本の筋金入りのファイナルファンタジー愛があった。
特に「ファイナルファンタジー11」への愛着は尋常ではなく、7年間に渡ってプレイし続け、総プレイ時間は900日を超えるという驚異的な記録を持っている。
堂本自身は「”廃人”のように、めちゃめちゃやり込んでいました」と当時を振り返り、「2時間くらい人が集まらなかったりするんですけど、その原始的な感じも好きでした。多分俺、”ドM”なんで。『この装備取るために何時間、いや何年かけんねん』っていう」と語っている。
この深すぎるゲーム愛は、スクウェア・エニックス社内でも有名で、同社の野末武志氏は「社内でも光一さんのFF好きは有名で、『何か取り組みができないか』という話があったんです」と明かしている。
アルバム「PLAYFUL」に込められたファンタジー世界観
2021年発売のアルバム「PLAYFUL」では、堂本の考える「遊び心」を最大限に表現し、ファイナルファンタジーの世界観が色濃く反映された。
特に注目すべきは収録曲「V(ファイブ)」で、これはスクウェア・エニックスのサウンド部所属の水田直志氏が作曲・編曲を担当したインストゥルメンタル楽曲である。
この楽曲には「壮大な物語が進行していくようなドラマチック」な雰囲気が込められており、まさにファイナルファンタジーの呪文や魔法のような神秘的な力を音楽で表現したものとなっている。
「V Short Movie」での表現
初回盤A特典として収録されたショートムービー「V Short Movie」では、堂本が王と影武者の1人2役を演じ、人間と物の怪との争いを描くハイスピード剣劇が展開される。
この映像は堂本本人のモーションキャプチャを含む実写とフルCGのハイブリッド技術で制作され、ファイナルファンタジーシリーズで培われたCG技術の粋を集めた作品となった。
最新アルバム「RAISE」への影響と継承
2025年9月10日にリリースされた約4年ぶりの6thアルバム「RAISE」においても、前作で確立されたファンタジー世界観の影響は色濃く残っている。
アルバムタイトル「RAISE」は「気持ちを高める、盛り上げる、励ます」といった意味を持ち、これはファイナルファンタジーシリーズの回復・支援系呪文の概念と通じるものがある。
実際に、ファイナルファンタジーシリーズにおける「レイズ」系の呪文は、戦闘不能状態の仲間を蘇生させる重要な魔法として位置づけられており、堂本の音楽活動においても「新たな一歩」をテーマとした再生・復活の象徴として機能している。
リード曲「The beginning of the world」
リード曲「The beginning of the world」のミュージックビデオでは、総勢51名による壮大なパフォーマンスが展開され、まさに「世界の始まり」というタイトルが示すように、ファンタジーRPGの世界創世を思わせる壮大なスケール感が表現されている。
ファンの反響と文化的影響
堂本光一のファイナルファンタジー愛とアルバムに込められた世界観は、多くのファンから熱狂的な支持を受けている。
特に「V Short Movie」については、「これぞ、堂本光一ワールド!!この作り上げられた世界観はMVだからこそ!」「異世界に光一さんが違和感なく存在してます」といった評価を受けており、彼独自のファンタジー世界観の構築に成功したことが伺える。
また、ファンの間では「ザビギが公開されたときに弟とFFのボス戦っぽいという話とニーアっぽいという話になりました。コーラスがとてもゲームミュージックぽい雰囲気」といった反応も見られ、楽曲レベルでもファイナルファンタジーの影響が感じ取られている。
今後の展開への期待
堂本は過去のインタビューで「今回(のコラボ)ができれば序章であってほしい。まだまだ無限の可能性があると思う」と語っており、スクウェア・エニックスとの更なる展開にも前向きな姿勢を示している。
実際に、同社ゲームへの出演について問われた際には「それはもう、チョイ役でも、声の出演だけでも、本当にやらせていただきたい。宿屋のおっさんとか…」と具体的な希望を述べるなど、今後の可能性に対する強い意欲を見せている。
アルバム「RAISE」の成功により、堂本光一の音楽活動におけるファンタジー世界観は更に深化し、日本のエンターテインメント界における新たな表現手法として注目を集めている。
彼の音楽に込められた「ファイナルファンタジーの呪文」は、単なるゲーム愛を超えて、芸術的な昇華を遂げた稀有な例として、今後も語り継がれていくことだろう。
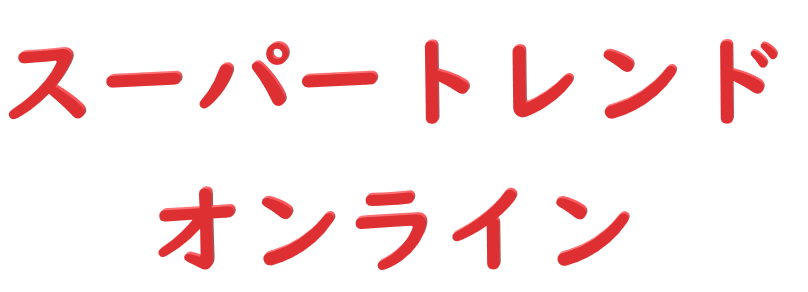
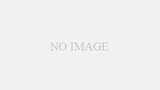
コメント