「えもんかけ」という言葉を、
最近耳にしたことがあるだろうか。
かつては着物用の道具や、一般的なハンガーを指す呼び名として広く使われていた。
しかし今では、昭和後期以降、若い世代の言葉遣いからすっかり消えつつある。
本記事では、着物文化の衰退や洋服の普及といった社会背景を踏まえつつ、
「えもんかけ」がいつ頃まで日常語であったのかを探っていく。
衣紋掛け(えもんかけ)とは何か
漢字表記と由来
「えもんかけ」は漢字で「衣紋掛け」と書く。
「衣紋(えもん)」は着物の襟元の形状を指し、
「掛け」は衣服を掛ける道具を意味する。
つまり、和服の衣紋を崩さずに形を保つための道具全般を表していた。
和服文化が盛んだった平安時代にはすでに存在し、
江戸時代以降、武家や商家の礼装保管に欠かせない道具として定着した。
具体的な形状と用途
当初は割竹や矢竹で作られる幅広の棒に、
袖を通す紐がついたシンプルな形状であった。
現代のプラスチック製ハンガーとは異なり、
着物の重さを支えつつ通気性にも優れていたのが特徴である。
また「衣桁(いこう)」と呼ばれる家具状の掛け台も、
同様に「えもんかけ」と混同されることがあった。
「えもんかけ」が日常語から消えた背景
和服離れと洋服普及の波
昭和30年代以降、洋服文化が急速に広がり、
日常生活で着物を着る機会は激減していった。
同時に、輸入品を含むハンガーが安価かつ大量生産され、
家庭の衣類管理ツールとして主流となった。
竹製の衣紋掛けは高価で扱いに手間がかかるため、
次第にプラスチック製ハンガーに置き換わっていった。
用語としての死語化
若い世代にとって「えもんかけ」は知らない言葉となり、
昭和末期から平成初期にはすでに日常会話で使われる機会がほぼなくなっていた。
調査によれば、大学生の約80%が「えもんかけ」という単語を知らないという結果もある。
このことから、1980年代後半から1990年代初めまでに、
一般語としての使用は実質的に消滅したと考えられる。
まとめ:いつから使われなくなったのか
「えもんかけ」という言葉が実質的に死語化したのは、
昭和後期から平成初期にかけての30~40年ほど前である。
和服の着用機会が激減し、洋服用ハンガーが主流となったことで、
日常語としての地位を完全に失った。
以上、古語ともいえる「えもんかけ」が日常から姿を消した背景と時期を解説した。
当時を知る世代の言葉遣いの痕跡として、今もなお伝承していきたい呼称である。
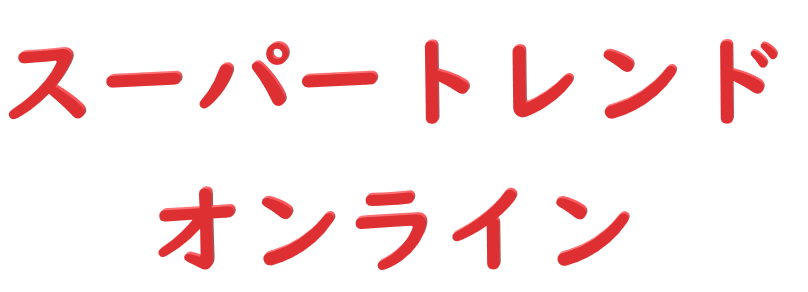
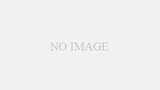
コメント