2025年12月26日(金)、深緑野分の人気小説を原作とする劇場アニメーション『この本を盗む者は』が全国で公開される。
「この本を盗む者は?」という疑問に対する答えは明確だ——はい、原作があります。
2020年に角川文庫から刊行された深緑野分による同名小説が原作であり、2021年の本屋大賞にもノミネートされた作品である。
原作小説について
『この本を盗む者は』は2020年10月8日にKADOKAWAの角川文庫から刊行された。
著者の深緑野分は『戦場のコックたち』『ベルリンは晴れているか』で知られており、歴史とミステリーの融合で高く評価されてきた。
本作では、これまでの作風を一変させて、ファンタジーという新しいジャンルに挑戦している。
物語の舞台は「書物の街」として知られる読長町(よむながまち)。
曾祖父が創立した巨大な書庫「御倉館」を代々管理する一家に生まれながら、当人は本が好きではないという矛盾を抱えた主人公・高校1年生の御倉深冬。
御倉館から蔵書が盗まれたことをきっかけに、町全体が本にかけられた呪い「ブックカース」に侵食され、物語の世界へと姿を変えてしまう。
物語を救うため、突然現れた謎の少女・真白(ましろ)とともに、本泥棒を追って様々な物語の世界を冒険する深冬。
その旅の中で、彼女は呪いの真実と、自分が知らなかった御倉家の秘密に迫っていく。
短編的な複数の物語を組み合わせながら、次第にその全体像が明かされていく構成は、多くの読者を魅了した。
「ブックカース」——古き知識と現代ファンタジーの融合
本作の核となる「ブックカース」という概念は、フィクションではなく、実際の歴史に根ざしている。
印刷機が存在しなかった中世ヨーロッパでは、本は極めて貴重な財産であり、修道士たちが手書きで写本を製作していた。
本に書かれた誤字脱字さえも「悪魔の仕業」と信じられるほど、神聖で大切な存在だったのだ。
そうした時代、本の所有者を明記し、盗難を防ぐために用いられたのが「蔵書票(エクスリブリス)」である。
本の所有者は、蔵書票にこう記した。
「この本を盗む者は、足の小指を戸棚にぶつけて悶絶しろ」「ハリネズミにキスされるだろう」——本を盗むことの危険性を、ユーモアを交えながら、あるいは呪いの言葉を通じて、泥棒に対する警告とした。
この古い伝統的知識を、深緑野分は巧みにファンタジーの世界へと組み込んだ。
本を盗む者を呪う言葉は、単なる冗談や警告ではなく、実際に魔力を持つようになる。
本作では、ある人物がこの「本の呪い」を本気でかけることで、事件の幕が上がるのである。
本屋大賞ノミネート——多くの書店員に選ばれた理由
2021年の本屋大賞ノミネートは、本作の文学的価値を示す証だ。
全国の書店員が選ぶこの賞は、単なる商業的成功だけでは選ばれない。
本作が深く評価された背景には、古い知識と現代の高校生の冒険を融合させ、「本とは何か」「物語とは何か」を問い直す深さがある。
本嫌いの少女が、実は本から逃げるしかなかった理由——亡き祖母の遺したトラウマ——にどう向き合うのか。
町を救うために、深冬は自らが最も避けてきた「物語」の世界へと足を踏み入れることを強いられる。
この逆説的な構造が、多くの書店員、そして読者の心をつかんだのだろう。
メディアミックス展開——漫画化を経て映画化へ
原作小説の成功を受けて、本作は積極的にメディア展開されてきた。
2020年の刊行後、口コミでじわじわと人気を集め、話題作として認知が広がっていく。
その流れの中で、より広い層に物語を届けるための手段として選ばれたのがコミカライズだ。
漫画版では、テキストと挿絵だけでは表現できなかった登場人物の表情や世界観がビジュアルで立ち上がる。
読長町の独特な雰囲気、御倉館の圧倒的な蔵書の量、物語世界へと変貌した町の様子などが、コマ割りと画面構成を通じてダイナミックに描かれる。
活字ではイメージしづらかった部分も、視覚情報として入ってくることで理解しやすくなり、原作読者からも好意的な評価を得た。
さらに2025年、ついに劇場アニメーション版が公開される。
監督は『ラディアン』『神クズ☆アイドル』などを手がけてきた福岡大生。
キャラクターデザイン・作画監督には、アニメーションファンから支持を集める黒澤桂子が抜擢されている。
アニメーション制作を担当するスタジオかごかんは、オリジナル色の強い作品でも定評があり、繊細な感情表現とファンタジックなビジュアルの両立が期待されている。
映画版の基本情報
劇場アニメ『この本を盗む者は』は、2025年12月26日(金)より全国公開となる。
公開時期は年末ということもあり、冬休みの映画館に足を運ぶ学生や社会人にとって、ちょうど良いタイミングだ。
原作ファンだけでなく、「本」や「物語」が好きな幅広い層にアピールできる時期と言える。
メインキャストには、映画・ドラマで活躍する若手俳優と実力派声優が名を連ねる。
本嫌いの女子高生・御倉深冬役を演じるのは、注目の若手俳優・片岡凜。
犬耳を持つ謎の少女・真白役には、子役時代からキャリアを積んできた田牧そらがキャスティングされている。
アニメファンにおなじみの声優陣も多数出演する。
深冬の母・御倉ひるね役を東山奈央、父・御倉あゆむ役を諏訪部順一、町のキーパーソンとなる与謝野蛍子役を伊藤静が担当。
さらに、深冬の心に大きな影響を残した祖母・御倉たまき役として朴璐美が出演しており、物語に重厚感を与えている。
音楽面では、主題歌をYUKIが担当する。
YUKIの透明感と芯の強さを併せ持つ歌声が、「本が嫌い」だった深冬の葛藤や、物語の世界での成長と重なり、エンディングを鮮やかに彩る。
劇伴もまた、読長町の静謐さと、物語世界の非現実感を行き来するようなサウンドで構成されており、映像とのシナジーが期待される。
原作者による映画観賞前ガイド
映画公開を控えた2025年12月、原作者・深緑野分はnoteに「映画『この本を盗む者は』観る前ガイド!!その①」という記事を公開した。
このガイドは、映画をより楽しむために必要な最低限の予備知識をコンパクトにまとめたもので、作品の世界観や背景を補足してくれる。
深緑野分は、その記事の中で「映画は試写で4回観た」と明かしている。
原作者が複数回の試写を経て「とても楽しい」「一ファンとしても推したい」と感じるほどの仕上がりになっていることがうかがえる。
一方で、「原作には存在するが、映画では説明を省いた部分がある」「本のジャンルに関する専門知識が必要な展開がある」といったポイントにも触れている。
つまり映画版は、原作の全てをそのまま映像化しているわけではない。
限られた上映時間の中で物語をまとめ上げるため、いくつかの説明や背景描写を思い切ってカットし、映像的なインパクトとテンポを優先している部分があるということだ。
そこで原作者は、観客が戸惑わないように、ネタバレにならない範囲で「知っておくと理解しやすくなるポイント」を事前に共有している。
映画ならではの見どころ
映画版最大の特徴は、やはり映像ならではの「本の世界」の表現にある。
御倉館の書架がどこまでも続く圧巻のビジュアル、本のページがめくれるとともに現実の町が別世界へと変貌していく演出などは、文章では想像するしかなかったシーンを一気に「体感できるもの」へと変えている。
また、町全体が物語に飲み込まれるという設定は、アニメーションの強みを最大限に生かせる。
空の色が変わり、建物が紙のようにめくれ、道路が行間のように裂けていく様子など、現実世界では再現が難しい表現も、アニメであれば自在だ。
深冬と真白が本の世界を駆け抜けるアクションシーンも、軽快なカメラワークとスピード感のある作画で魅せてくれるはずだ。
登場人物の感情表現にも注目したい。
本が嫌いだと語る深冬のぎこちなさ、祖母の死にまつわるトラウマ、家族への言葉にできない本音などが、表情やちょっとした仕草として画面に刻まれる。
文字情報だけでは読み取りきれなかったニュアンスが、声優の演技と作画によって立ち上がり、キャラクターが「生きている人間」として迫ってくる。
Xでの反応とトレンド感
公開直前から、Xでは『この本を盗む者は』についての投稿が徐々に増えている。
試写会やプレミア上映に参加したユーザーのポストでは、「今年一番のカルトアニメ映画になるのでは」「展開のスピード感がとにかくすごい」といったコメントも見られ、コアな映画ファンの間で早くも注目作として位置づけられ始めている。
特に、物語の構造的な面白さに言及する声が目立つ。
「理解する前に次の展開が来るのに、最後に全部つながる感じが気持ちいい」「本に関する知識がちょっとあるだけで、あちこちに仕込まれたネタにニヤニヤできる」といった感想からは、本作が単純な冒険譚ではなく、メタ的な仕掛けに富んだ作品であることがうかがえる。
また、アニメファンの層からは作画面への評価も上がっている。
「紙の質感やインクのにじみ方が細かく描かれていて、画面から紙の匂いがしてきそう」「本の世界に入る瞬間のエフェクトが何度見ても気持ちいい」といった声は、劇場の大スクリーンでこそ味わいたいポイントだ。
劇場で楽しめる施策
劇場展開にあわせて、来場者向けの特典施策も用意されている。
公開から一定期間、来場者には限定の小冊子やポストカードが配布される予定だ。
特典の内容は、作品世界をより深く楽しめるような設定資料や、原作者からのコメントなど、ファン心をくすぐるものになっている。
また、一部の劇場では公開初日から舞台挨拶付き上映やトークイベントも予定されている。
キャストや監督、さらには原作者が登壇する回もあり、制作秘話や作品への思いを直接聞くことができる機会となる。
映画を観るだけでなく、その裏側にある創作のプロセスまで知ることで、物語をさらに深く味わえるだろう。
「これだから本は嫌いなのに」——冒険の始まり
作中に登場する「これだから本は嫌いなのに」という印象的なフレーズは、本が苦手な人間の本音を鋭く突いている。
分厚くて読むのが大変、専門用語が難しい、途中で挫折してしまう——そんな経験がある人にとって、この一言は共感の一歩目となる。
しかし物語が進むにつれて、この言葉の意味は少しずつ変化していく。
本の世界に巻き込まれ、逃げ出したくなるような理不尽さや危険と向き合いながらも、深冬は物語の中で出会う人々や出来事を通じて、「物語に救われる瞬間」もまた確かに存在することを知っていく。
本が嫌いだったはずの少女が、「それでも本を手放したくない」と思うようになるまでの心の変化。
その過程こそが、本作の核にあるテーマだ。
劇場版がどこまでその変化を描き切るのか、原作既読勢も未読勢も、スクリーンで確かめたくなるはずである。
原作と映画、どちらから触れるべき?
「原作と映画、どちらから触れたほうがいいか」という悩みは、多くの人が抱くところだろう。
『この本を盗む者は』の場合、どちらから入っても楽しめるように設計されているが、それぞれにメリットがある。
先に原作を読む場合、物語の構造や設定、登場人物の背景をじっくり味わうことができる。
映画で描かれない細部や、内面の機微まで理解したうえで映像化作品を観ると、「このシーンをこう表現したのか」「ここはあえて省略したのか」といった比較の楽しみが生まれる。
一方で、先に映画から入ると、情報量を整理する前に怒涛のような展開に飲み込まれる体験ができる。
何が起きているのかを追いかけながら観る感覚は、まさに「物語の渦中に放り込まれた登場人物」と同じだ。
観賞後に原作を読むことで、映画では語られなかった行間が埋まり、再度作品世界に浸ることができる。
「この本を盗む者は?」への答え
あらためて、「この本を盗む者は?」という問いに立ち返ってみよう。
結論から言えば、それは単なるキャッチーなフレーズではなく、「本を盗む者への呪い」として実在した文化的背景を持つ言葉だ。
中世の写本文化から生まれたブックカースは、「知識へのアクセスが限られていた時代に、本を守るための最後の手段」として機能していた。
深緑野分は、その歴史的モチーフを現代ファンタジーの枠組みの中で再構築し、「本の呪い」と「物語の力」という二つのテーマを描き出した。
劇場アニメ版『この本を盗む者は』は、その原作をベースにしながらも、映像作品としての面白さを前面に押し出している。
本作に触れるとき、「この本を盗む者は?」という問いは、やがて「この物語を手放せない者は?」という、少し違うニュアンスの問いへと変化していくはずだ。
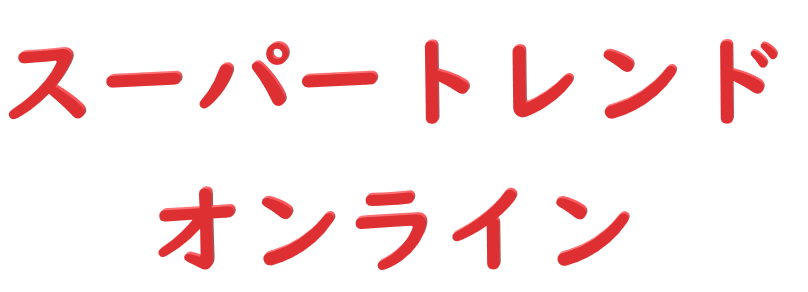

コメント